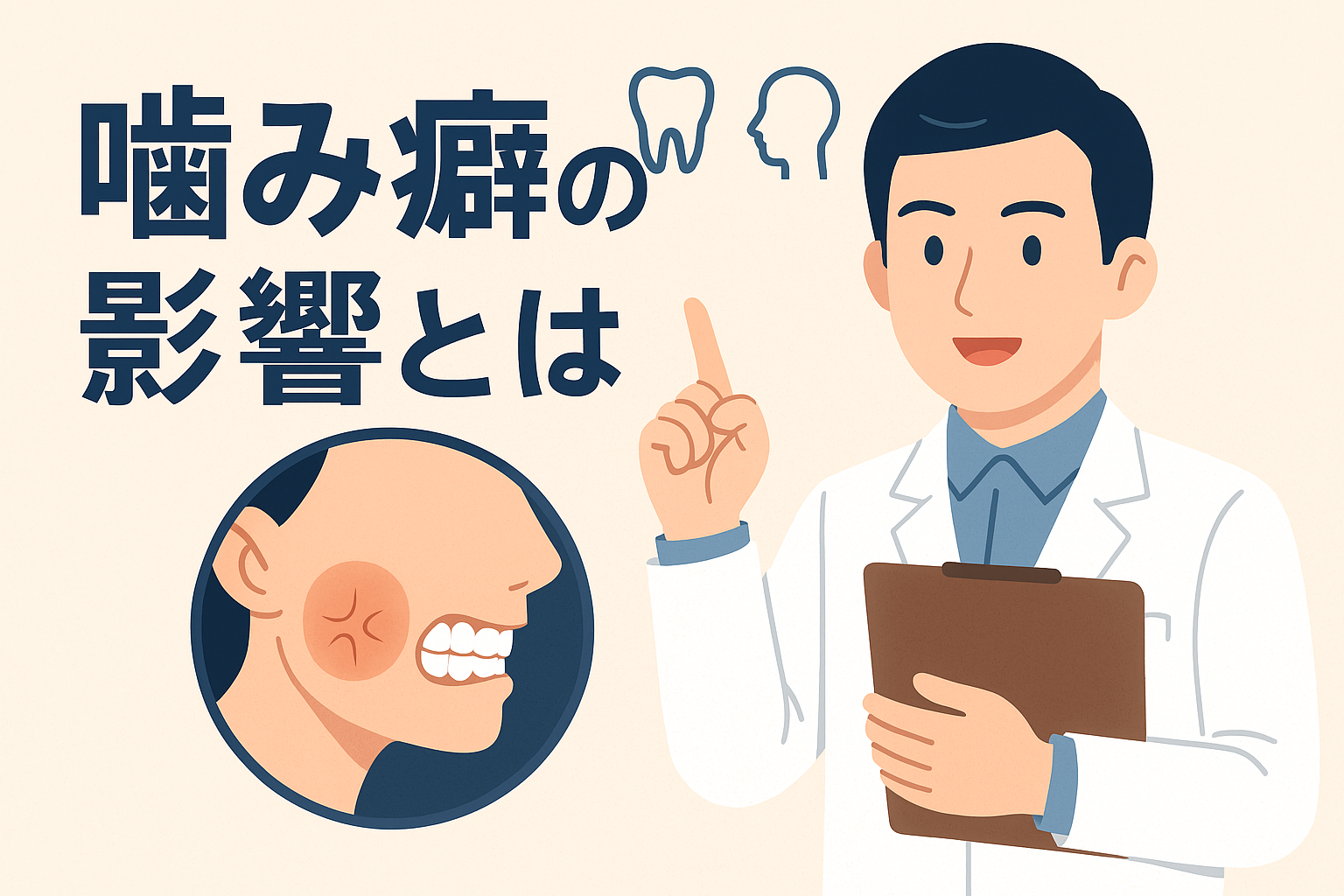お口の中気になる!?口腔内の善玉菌を増やしてむし歯・歯周病を予防しよう🦷🪥
 歯科ブログ
歯科ブログ
2025.10.05
こんにちは。箕面市牧落オートバックス前、ヨコヤマ歯科の保育士の岡本です🍀
口腔内には数百種類もの細菌が棲んでいますが、その中で頼もしい役割を果たしているのが善玉菌です。善玉菌が多いと、むし歯や歯周病のリスクを下げることができます。しかし、現代ではこの善玉菌が活躍しやすい環境を保つことが難しくなっています。
今回は、善玉菌を増やすための食生活や口腔ケアについて解説します。

目次
口腔内の善玉菌とは?その役割と重要性
口腔内には、善玉菌・悪玉菌・日和見菌(ようすを見て味方になる菌)が共存しています。
善玉菌は、以下のような働きで口腔環境を守る存在です:
• 酸性に傾いた口内を中和する働きを助ける
• 悪玉菌(むし歯菌、歯周病菌)の過剰増殖を抑える
• バイオフィルム(プラーク)の質をコントロールする助け
• 免疫反応を調節し、炎症を抑える方向に寄与する可能性
逆に、生活習慣・食生活・口腔乾燥などで善玉菌が減少すると、悪玉菌が優勢になりやすく、むし歯や歯周病、口臭のリスクが高まります。
また、善玉菌の代表例としては ラクトバチルス属菌、ストレプトコッカス・サリバリウス、アクチノマイセス属 などがあり、これらは口腔内の健康維持に寄与する可能性があるとされています。
善玉菌を増やすための具体的なケア方法
食生活の見直し:発酵食品・食物繊維を意識
• 無糖ヨーグルト・乳酸菌飲料(無糖タイプ)
砂糖添加が少ない製品を選ぶことで、むし歯リスクを抑えつつ善玉菌を補給できます。
• 発酵食品(納豆、みそ、漬物など)
発酵食品には菌の働きやすさを助ける成分が含まれていることがあります。
• 食物繊維・プレバイオティクス食品
ごぼう、きのこ、海藻、オリゴ糖などは善玉菌の“エサ”になりやすく、定着を促す可能性があります。
• よく噛む習慣を持つ
咀嚼を増やすことで唾液分泌が促され、清浄作用・中和作用を高められます。
マイルドな口腔ケア法:善玉菌を残す配慮
• 強すぎる殺菌タイプの洗口液を毎日使うと、善玉菌まで抑えてしまう可能性があるため、使用頻度を抑えるか弱めのタイプを選ぶ。
• フッ素配合の歯磨き粉を使いながら、過度な研磨剤使用は避ける。
• 歯ブラシや歯間ブラシ、フロスなどによって機械的除去を丁寧に行い、バイオフィルムをコントロールする。
• 定期的なプロフェッショナルクリーニング(PMTC や歯石除去)を受けることで、善玉菌が活躍できるベースを整える。
唾液量を増やす・乾燥対策
• 水分補給をこまめに
口腔が乾燥しないように、日中は適度に水を飲む習慣をつけましょう。
• 口呼吸を避け、鼻呼吸を意識
口を閉じて鼻で呼吸することが、口内の湿度保持に役立ちます。
• ガムやキシリトールガム、唾液腺マッサージなど
これらは唾液分泌を刺激する手段になり得ます。
注意すべきこと・やってはいけないこと
• 過剰な抗菌・殺菌ケア:必要以上に強力な殺菌剤を毎日使うと、善玉菌も減ってしまうリスクがあります。
• 高糖質・間食の多さ:砂糖や加工食品の過剰摂取は、悪玉菌の栄養源になるためバランスを崩しやすいです。
• 喫煙・過度な飲酒・ストレス:これらは口腔の防御機能を低下させ、善玉菌の働きを妨げる可能性があります。
• 唾液分泌が少ない人(ドライマウス傾向):基本対策(保湿、唾液促進)を意識する必要があります。
定期歯科検診との併用の意義
善玉菌ケアはあくまで「補助的な予防手段」として有効ですが、完全ではありません。プロによる検診・クリーニングを定期的に受けることで、見落としやすいむし歯や歯周病の初期兆候を早期発見できます。
善玉菌を増やす日常ケアと、歯科医院でのプロフェッショナルケアを組み合わせることで、お口の健康をより強固に守ることができます。
まとめ:日常に取り入れたい善玉菌ケア習慣
• タイトルキーワード「口腔内の善玉菌を増やす」「むし歯・歯周病予防」は、導入部・見出し・まとめ部などで自然に繰り返す
• 無糖ヨーグルトや発酵食品を取り入れ、良い菌の栄養になる食材を選ぶ
• 過度な殺菌ケアを避け、マイルドな口腔ケアを心がける
• 口腔の乾燥を防ぎ、唾液分泌を促す
• 定期検診・クリーニングを必ず併用する
お口の中で気になる事があれば、ぜひ一度ヨコヤマ歯科へお越しください😊